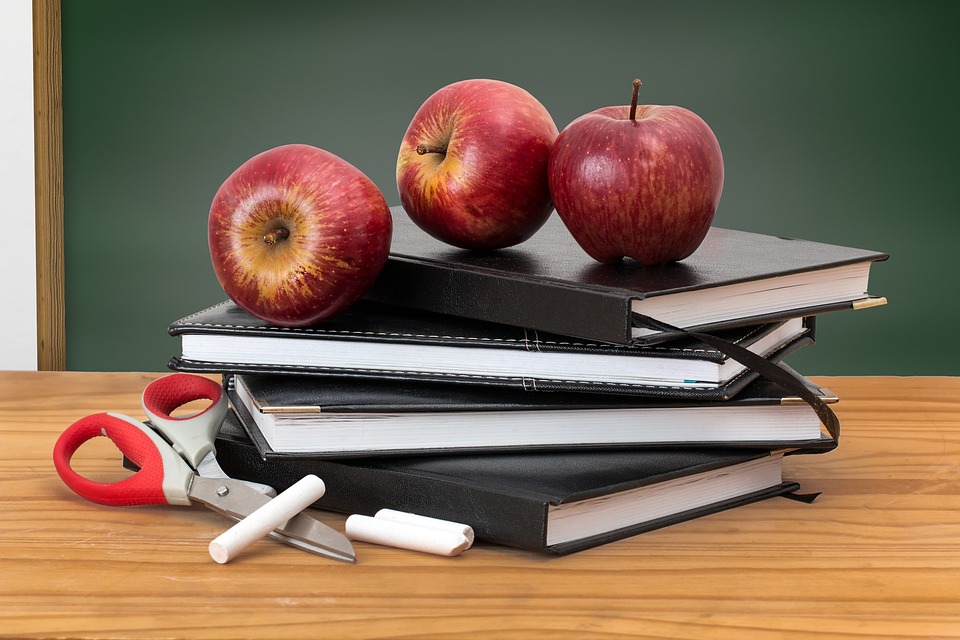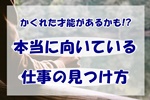授業再開後、教員にとっていちばん大切なことは、
新型コロナから子どもたちを守ること。
そのためには、教員は新型コロナの感染防止に努めなくてはなりません。
教員10年目で、新型コロナから子どもたちを守るための情報を毎日チェックしています。
この記事では、こんな疑問に答えます。
この記事を読めば、授業再開後に、子どもたちを新型コロナから守るヒントを得ることができます。
新型コロナから子どもを守る対策をきちんととれば、教員も子どもも楽しく、授業をすることができます。

【コロナ禍から授業再開】小学校で子どもたちを守るためには
子どもを新型コロナから守るためには、当たり前のこととなっていますが、
3密(密閉、密集、密接)を避ける
CLINIC FOR渥美義大 医師によると、3密を避けるとは、次のようになります。
- 密閉を避ける・・・窓がなかったり換気できなかったりする場所を避ける
- 密集を避ける・・・人が集まったり、少人数でも近い距離で集まることを避ける
- 密接を避ける・・・互いに手が届く距離での会話や発生、運動を避ける
子どもたちを新型コロナから守るには、この3密を避けることが絶対条件となります。
【新型コロナから子どもを守る】小学校の教員がやってはいけない8つとは
- 対話的な学習をすすめる
- 学校の備品を共用する
- 児童に集合・整列の号令をかける
- 給食で向かい合って食べさせる
- 教室の窓を1つだけ開ける
- 広い体育館の扉を閉める
- 子どもに体力的な無理をさせる
- コロナにかかった人を悪とする
文科省のガイドライン(4月6日時点)を参考にまとめてみました。
対話的な学習をすすめる
授業でペアトークやグループトークを行う
「主体的・対話的・深い学び」元年であっても、今は子ども同士がお互いに顔を向き合って授業をするのは控えるべきです。
学校の備品を共用する
顕微鏡を使うときに、子ども同士で集まって観察する
班で1つのものを用意するのは危険です。
とくに、理科の学習は、子どもの興味関心が高いので、集まらないというルールがあっても、子どもが夢中になって集まってしまう可能性が高いです。
備品は、個人で1つ用意することを心がけましょう。
児童に集合・整列の号令をかける
体育で、離れて活動していた子たちに集合の号令をかける
学校は集団生活を基本とするので、コロナ前は、子どもが集合して話を聞いたり、指導を受けるのは当たり前でした。
しかし、今後、子どもが集まらなくても指導ができる方法を、教員は考えなければならなりません。
給食で向かい合って食べさせる
机の配置を島型にして、お互いが向かい合って食べる
向かい合って食事を食べると、感染症拡大につながります。
授業を受けるときと同じように、子ども全員が同じ方向を向いて、間隔を空けて、個人の隊形で食べるようにしましょう。
また、給食前の手洗い、うがいの徹底を図り、食事中も換気の必要があります。
教室の窓を1つだけ開ける
開放する窓を1つだけにして、他の窓は閉め切る
開放がした窓が1つだけだと、空気の流れが止まります。
空気の流れをうまく作るには、窓を2か所以上開ける必要があります。
換気をするときは、空気の流れを意識しましょう。
体育館の扉を閉める
広い体育館だからといって閉め切って活動する
天井が高く、広い体育館でも換気の必要があります。
文科省のガイドライン(4月6日時点)でも、体育館の換気を行うように書かれています。
子どもに体力的な無理をさせる
休校中に体力が落ちた児童に無理をさせる
2月27日に休校が発表されてから、2カ月以上、子どもたちは学校を休んでいます。
体力は当然落ちていると考えられます。
体育で、こまめにゆとりの時間を取り入れるなど、体力が落ちた子どもへの配慮が必要です。
新型コロナにかかった人を悪とする
新型コロナにうつった人を悪く言う
新型コロナは非常に感染力の高いウイルスです。
いつ、誰が新型コロナにかかるか分かりません。
新型コロナにかかった人への差別がないように、子どもたちに指導をしていく必要があります。
新型コロナにかかった人が悪いのではなく、新型コロナウイルスが悪いのです。
新型コロナに感染させない授業の方法とは
新型コロナに感染させない授業の方法は、たった1つ。
3密を避ける授業方法
国語
唇(くちびる)読みや黙読の活用
唇読みとは、くちびるだけを動かして読む音読方法。
ほとんど聞こえないくらいの声で音読する。もしくは、黙読をする。
算数
ICT活用や視覚的支援の活用
黒板の掲示物を増やしたり、動画やスライド教材を使って、見た目で分かりやすくする。
話し合いや議論によって、学習を進めることが難しくなるので、視覚的支援を増やす。
社会
動画教材や資料集の活用
分かりやすい動画や見やすい資料集で、視覚的情報を増やす。
教科書や資料を見て、考えをまとめる時間の充実を図りましょう。
理科
実験器具や観察物を個人分で用意する
「班で1つ」といった器具の用意の仕方を避け、なるべく個人で1つずつ用意するようにしましょう。
どうしても、個人で用意できないものについては、使用後に手洗いをするようにしましょう。
英語
ライティングやリスニングの時間を充実させる
本来、小学校の英語は、表現力を高めることが重要です。
しかし、新型コロナのことを考えると、スピーチやトークといった形の学習は難しくなります。
単語をなぞって書いたり、CDの音声を聞く活動の充実を図りましょう。
図画工作
個人製作、鑑賞の時間の充実
図工は、個人で取り組むことが可能な教材が多い科目です。
個人でじっくりと取り組むようにしましょう。
また、コロナ対策を機会に、鑑賞の時間にもたっぷりと時間をかけましょう。
鑑賞なら、おしゃべりが少なくなります。
代表的な名画をカラー印刷して、良さや特徴を感想シートに記入していく活動がおすすめです。
体育
- 集合する位置にマーカーを置く
- なわとびの活動を増やす
子どもたちは、これまでの経験から集合の号令がかかると、密になった集合隊形になりがちです。
体育では教師の号令で密にならないようにする必要があります。
縮みジャンケン
①二人組でジャンケン
②負けた人は「縮む縮む」と言いながら、10㎝くらいしゃがむ。
③ ①②の繰り返し。(相手を変えるバージョンもあり)
④ひざかおしりが床に着いたら人の負け。これはスクワット効果も期待できそうw
筋トレもできて楽しいジャンケン。— 冷やしトマト (@shinhamuteki) May 18, 2020
音楽
歌わない歌唱の授業づくりをする
範唱CDを活用した「歌わない歌唱の授業」にチャレンジしてみましょう。
詳しくは、教育技術の「音楽指導のプロ教師が提案!新型コロナ対応の授業アイデア」をご覧ください。

まとめ【コロナ禍から授業再開】小学校で子どもたちを守るためには
聞くや書く活動に重点を置く
しばらくは、コロナ対策を考えると、聞くや書く活動に重点を置いて、子どもの力を伸ばしましょう。
子どもたちが今、聞く力、書く力が身につけば、コロナ明けでは、子どもたちの話す力や表現力が飛躍的に伸びていくこととなります。
コロナ禍でも、子どもたちの力を伸ばしていきましょう。